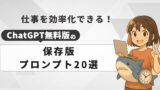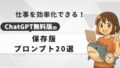昨今気軽に使えるAIツールが増えました。その中でも「生成AI」を利用したことがある方は多いのではないでしょうか?
質問を投げかけるだけで文章ができたり、思い描いたイラストが一瞬で形になったりと、とても便利で楽しいですよね。
一方で「AIが勝手に人の絵を学習している」「作ったものを公開したら著作権違反になるのでは?」といった不安の声も少なくありません。実際に海外では訴訟も起きています。
そこでこの記事では、初心者が最低限知っておくべき「生成AIと著作権」の基本をわかりやすく解説します。
注意すべき点と安心して使えるポイントをまとめたので、SNSやブログ等で安心して活用したい方は、ぜひ参考にしてください!
「これって著作権侵害!?」と不安になった時の確認方法も紹介しています!
なぜ著作権トラブルが起きるの?
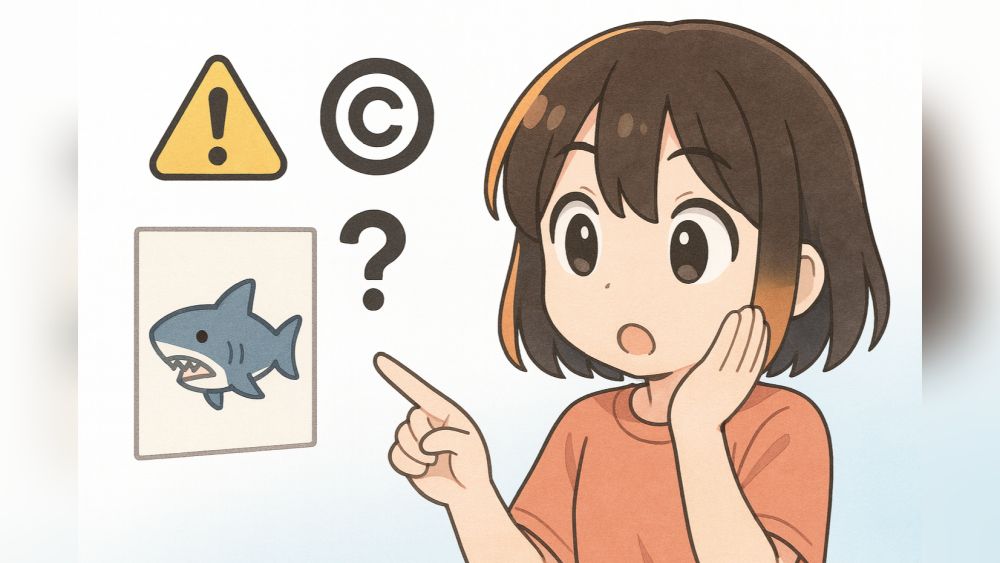
生成AIから、なぜ著作権トラブルが起きるのか不思議に思う人もいるでしょう。
実はAIが学習している仕組みや、そこから出力される結果に理由があります。まずは生成AIの基本についてわかりやすく整理してみましょう。
AIは人の作品を学んでいる
生成AIはインターネット上の大量の文章や画像を学習してできており、その中には「著作権で守られている作品=著作物」も含まれることがあります。
文化庁は「AIの学習自体は著作権法上、一定の条件下で認められている」としていますが、その結果として出力されたものが“誰かの作品にそっくり”に生成された場合、トラブルにつながってしまうのです。
似たものが出てしまうリスク
生成AIは「ゼロから完全に新しいものを作っている」のではなく、学んだパターンを組み合わせて文章や画像を生成しています。そのため、既存作品に似た要素が出力されるリスクは避けられません。
特にキャラクターデザインやイラストは似通いやすく、SNSで炎上するケースもあります。
最近は生成AI画像をプロフィールアイコンにしている方も多いですが、似ているデザインが多い印象です。
AI作品に著作権はあるの?
「生成AIで作ったものに著作権はあるの?」と気になる方は多いですよね。
ここでは文化庁の見解や海外の判例を交えながら、AI生成物に著作権があるのかどうかを初心者向けに解説します。
完全にAI任せ=著作権なし
文化庁の見解では、AIが完全自動で生成した作品には著作権は発生しないとされています。なぜなら、著作権が発生する条件として「人間の創作性」が不可欠だからです。
「AIが完全自動で生成した作品」とは、例えば下記のようなものが当てはまります。
- 画像生成AIに「猫」とだけ入力して作成された絵
- テキストAIに「物語を書いて」と入力して作成された小説風の文章
- 音楽AIに「短い曲を作って」と入力して自動で作成されたメロディ
このように細かい設定やアレンジが加わっていない生成物は、著作権が発生しません。
人が工夫や編集を加えた場合=認められる可能性あり
一方で、AIが作った文章や画像に対して、人が取捨選択・編集・加工を行い「創作性」が加わった場合は著作権が認められる可能性があります。
例えば「AIが生成した文章を基に、自分で構成を変えて記事にする」「AIが生成したイラストのポーズを変える、背景を描き足す」などの編集・加工を加えたものは、著作物とみなされるかもしれません。
海外判例の紹介(米国の事例)
アメリカでは、AIによって生成された画像の著作権をめぐり、裁判が行われた事例があります。
研究者Stephen Thaler氏が、独自のAIシステムによって自動生成された画像の著作権登録を申請しましたが、裁判所は「人間の創作性がない」として登録を認めなかったのです。
この判決は、「著作権は完全にAI任せで作られた作品には発生せず、人間による創作がなされているものにだけ発生する」ということを明確に示しました。
参考:Open Legal Community『Thaler v. Perlmutter判決:AIと著作権の境界線』
実際にあったトラブル
生成AIをめぐって、実際にトラブルになった事例もあります。
海外ではすでに裁判に発展しているケースもあり、日本でも今後増えていく可能性が高いです。
ここでは実際の事例について紹介していきます。
海外での訴訟事例
アメリカでは、AIの学習段階をめぐる著作権訴訟が相次いでいます。
例えば、Anthropic社が開発したAIモデル「Claude」は、自著が無断でAIの訓練に利用されたとして著名作家達により集団訴訟をされました。
音楽業界団体RIAAや各大手レコード会社も、音楽生成AIのスタートアップであるSuno社とUdio社に対して、楽曲が許可なく収集され学習に使われたとして裁判を起こしました。
つい最近(2025年9月)には、「Billboard」などの有名雑誌を発行するPenske Mediaが、Google社を提訴したのです。
Penske Mediaは、Googleで検索した際に検索結果の上部に出てくる「AIによる概要」が、発行元のコンテンツを不正に利用していると訴えています。
これらはいずれも、学習データの利用が適しているかどうかが争点となっています。
日本の現状(まだ判例は少ない)
日本でもAIをめぐる著作権紛争が出てきています。
円谷プロダクションは、中国企業による「ウルトラマン」によく似た画像を作成する生成AIに関して、コンテンツを無断利用したとして訴訟しました。
この件に関しては、中国の裁判所が著作権侵害を認め、損害賠償などを命じる判決を下しています。
また、読売新聞社は米国のAI検索サービス「Perplexity」が記事を無断で使用していると主張し、著作権侵害で訴訟しました。この件は現在も進行中で、非常に注目されている訴訟案件です。
ただし、こうした事例はまだ数が限られており、判例として確立されたものは多くありません。今後の動向を注意深く見ていく必要があります。
最近ではOpenAI社の動画生成AI「Sora」が、日本のアニメ作品などを無断で学習しているとSNSで炎上していました。こちらは現在修正対応されています。
トラブルを避けるためのチェックリスト
「どうすれば安心して生成AIを使えるの?」という方のために、具体的なチェックリストを用意しました。
SNSに投稿するときや商用利用を考えるときに役立つ、初心者にも実践しやすい内容です。
簡単な内容なので、公開する前にチェックしてみましょう!
SNSやブログに投稿する場合
AIで生成したものをSNSやブログに投稿する場合は、下記の4点をチェックしましょう。
- 投稿内容が既存の著作物に酷似していない
- 投稿時に「AI生成」など、出典や制作方法を明示している
- 他人を傷つけたり誤解を招くような悪用の意図がない
- 投稿先の利用規約やガイドラインを事前に確認している
現状「AI生成表記」は必須ではありませんが、いつかは義務化されるかもしれません。
商用利用する場合
AIで生成したものを商用利用する場合は、下記の3点をチェックしましょう。
- 利用しているAIサービスの商用利用可否を確認している
- クライアントや顧客に対し、AIを使用した旨を明示している
- 他者の著作物を無断で含んでいないか最終チェックしている
商用利用をする時は特に注意が必要です!それこそ裁判沙汰になる可能性だってあります…😨
不安なときの確認方法
ブログ・SNSでの投稿時や商用利用時のチェックリストはクリアしたものの、まだ不安が残る…という場合は下記を確認してみましょう。
- 文化庁のガイドラインやQ&Aを一度読む
- 利用規約を定期的に見直している
- AI出力物をそのまま使わず自分の工夫を加えている
著作権トラブルを防ぐために必須なのは、文化庁のガイドラインの確認です。
生成AIの進化はめざましく、法律や規制などが追いついていない印象があるため、定期的にガイドラインは更新されるかもしれません。
しっかりと文化庁のガイドラインや各媒体・AIツールの利用規約をチェックすることで、トラブルを未然に防げるでしょう。
まとめ:生成AIを安心して楽しむために著作権について理解しておこう!
生成AIは楽しく便利ですが、著作権トラブルには注意が必要です。
この記事で紹介した内容のまとめは以下になります。
- 完全にAI任せで生成したものは著作権なし
- 人の工夫や編集を加えると著作権が認められる可能性あり
- 海外ではすでに訴訟事例あり、日本もグレーゾーンが多い状況
初心者でも安心して楽しめるように、トラブルを避けるためのチェックリストも紹介しました。
生成AIを利用して作成したものを公開する際に、ぜひ活用してみてください。
AIは「正しく使えば頼れる相棒」です。ルールを知って安全に使いこなしましょう!
👉 関連記事: